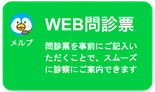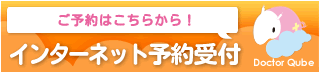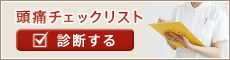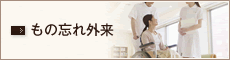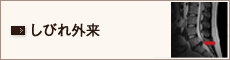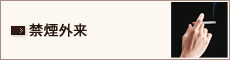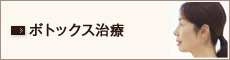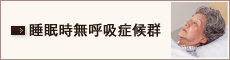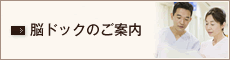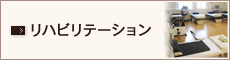薬剤の使用過多による頭痛
2022年04月09日
以前から頭痛があり1か月に15日以上存在し、頭痛薬を3か月以上にわたって飲んでいる場合を言います。
以前は薬物乱用頭痛と言われていました。
多くの方は片頭痛がベースにあります。
治療には、鎮痛薬をやめる必要がありますが、その間に予防薬の内服が有効です。
またベースにある片頭痛の治療が必要になってきます。
こくぶ脳外科・内科クリニック
高齢者てんかんと認知症
2022年04月02日
高齢になるとてんかん発作、認知症が起こりやすくなります。
アルツハイマー型認知症の場合、アミロイドやタウの蓄積が脳の起こってきます。それらが刺激になりてんかん発作を起こすことがあり、認知症を発症する前に発作を起こすこともあります。
高齢者の記憶が変動する場合、てんかん発作にも注意が必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
緊張型頭痛の非薬物療法
2022年03月19日
ガイドラインでは、頭痛の治療では薬による治療と薬以外の治療があります。
薬を使わない治療として精神療法、行動療法、理学療法、鍼灸などがあります。
薬が使えない方や、薬だけでは効果が十分でない場合は利用できる方法です。
慢性の頭痛の方は心因性の影響がある場合があります。
こくぶ脳外科・内科クリニック
頭痛とくも膜下出血
2022年03月12日
危険な頭痛の一つにくも膜下出血があります。
これは脳動脈瘤が破裂することにより頭蓋内に出血することで起こります。
片頭痛などの慢性頭痛は以前から定期的に起こる頭痛ですが、くも膜下出血は突然に起こる頭痛です。
中高年の方に多いですが、40歳前後の若年の方にも見られ注意が必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
手のしびれ
2022年03月05日
片方の手のしびれがみられる原因として、頸椎の椎間板ヘルニアがあります。
椎間板ヘルニアの場合は手の親指周囲にしびれがみられることが多いです。
MRI検査にて椎間板が神経を圧迫しているところを確認することができます。
しびれの原因として脳梗塞などが原因の場合もあり注意が必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
認知症の転倒 骨折
2022年02月26日
認知症の人は認知症のない人と比較して8倍転倒しやすくなり、骨折のリスクは3倍と報告されています。
特にレビー小体型認知症の場合はリスクが高くなります。
定期的な運動やバランス訓練を行って転倒予防が重要です。
薬剤の副反応などによりふらつきがみられる場合もあり注意が必要です。
高齢者では骨粗しょう症も伴っていることがあり、投薬加療が必要な場合があります。
こくぶ脳外科・内科クリニック
片頭痛による経済的損失
2022年02月12日
片頭痛に伴って仕事を休まざる負えなかったり、仕事中の生産性が低下することがあります。
それに伴う経済的な損失が年間に数千億円以上と言われています。
片頭痛に対して適切な治療が行われていない場合が多く、日本人の片頭痛患者の7割がまだ医療機関に受診していないようです。
最近では、新しい片頭痛の薬がでてきていますので、片頭痛で生活に支障のある方は一度病院受診してみてください。
こくぶ脳外科・内科クリニック
デイケアの勧め
2022年02月05日
デイケアは病院の付属の施設で、リハビリを中心に行っています。
高齢者で身体機能の低下がみられ介護が必要な方、または今後介護が必要になる可能性がある方が利用されます。
脳卒中の後の後遺症のある方、認知症のある方も適応になります。
今後さらに介護が必要にならないようにリハビリにて予防していくことが大切です。
認知症の進行予防にもリハビリによる全身運動は有効です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
痛み止めの使い過ぎによる頭痛
2022年01月22日
これは薬剤の使用過多による頭痛(MOH)と言われています。
いわゆる「頭痛薬」を飲みすぎることで頭痛が慢性化します。
特に1か月の半以上痛み止めを飲んでいる方にみられます。
片頭痛など慢性頭痛を持っている人は、いわゆる痛覚に対する過敏がありMOHになりやすいです。
痛み止めの飲みすぎで痛みに対する閾値がさがり、痛みを感じやすくなるために起こる現象です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
一時的に半身の動きが悪くなる
2022年01月15日
30分から1時間程度手足の動きが悪くなり、また動きだすようなことがあります。
これは「一過性脳虚血発作」の可能性があります。
一時的に脳の血管が詰まり症状がみられ、その後再開通することで症状が回復します。
しばらくしてから大きな脳梗塞を起こす可能性があります。
寒くなると脳梗塞のリスクが上がりますので注意が必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック