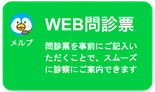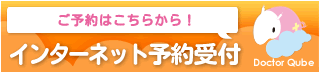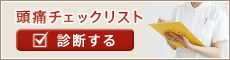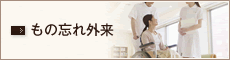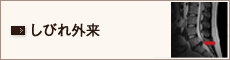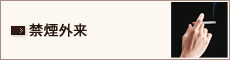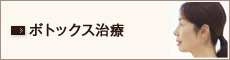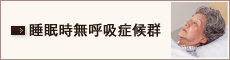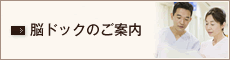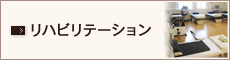乳幼児期の片頭痛
2018年05月12日
片頭痛は幼児の時から始まる場合もあります。
幼児の時は頭痛よりも、原因不明の下痢や嘔吐が見られます。
また乗り物酔いや起立性調節障害などの症状も片頭痛との関連が指摘されています。
小児周期性症候群として分類され、片頭痛に将来移行する場合があります。
小児の原因不明の嘔吐下痢、めまい症状は片頭痛の可能性もあります。
こくぶ脳外科・内科クリニック
頭痛のない片頭痛
2018年04月28日
病名は片頭痛なのに頭痛がないパターンがあります。
典型的な片頭痛の前兆があるものの頭痛を伴わない場合がそれに当たります。
前兆症状は、ギザギザしたものがみえる、しびれ感、脱力、失語、めまいなどです。
約30分程度持続しておさまるのが特徴です。
一過性の脳虚血発作でも同様の症状を示すことがあり、鑑別が大切です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
下の血圧について
2018年04月14日
血圧には上の血圧と下の血圧があります。
上の血圧は心臓の収縮期で、下の血圧は拡張期のものです。
下の血圧が高い場合と低い場合があります。
末梢の血管が硬くなってくると下の血圧が下がってきます。
高齢者の場合は比較的下の血圧が低い傾向にあります。
一方で若い人は血管が柔らかいので下の血圧が高い傾向にあります。
こくぶ脳外科・内科クリニック
くも膜下出血と意識消失
2018年04月07日
くも膜下出血の多くは脳の血管にできた脳動脈瘤が破裂して起こります。
動脈瘤が裂けた時の出血量によって状態が変わります。
出血量が少ない場合は軽い頭痛だけの時もあり、出血量が多い場合は意識がなくなることもあります。
くも膜下出血が原因で心臓が停止したりそのまま亡くなることもあります。
どの程度出血してしまうかは個人差でわかりません。
こくぶ脳外科・内科クリニック
高血圧と慢性頭痛
2018年03月24日
高血圧が原因で頭痛がすることがあります。
中高年になると血圧が上がってきますが、あまり血圧測定していない人が多いです。
頭痛が続くため病院を受診すると高血圧があり、自分でも気づいていない場合があります。
このような方に血圧を下げる薬を飲んでもらい、血圧を正常化させると頭痛がおさまる場合もあります。
また高血圧があると脳卒中の原因になるので注意が必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
妊婦とインフルエンザ
2018年03月17日
妊婦さんがインフルエンザにかかることはあります。
抗インフルエンザ薬は添付文書で「治療上の有益性が危険性を上回ると判断されり場合のみ投与すること」となっています。
妊婦さんがインフルエンザになると流産などの合併症リスクが高くなり、治療の必要性が高いと考えられます。
アメリカでは重症化予防で抗インフルエンザ薬の使用が勧められているようです。
こくぶ脳外科・内科クリニック
脳卒中による認知症
2018年03月09日
以前は脳卒中を繰り返すことで認知症になると考えられていましたが、臨床的に脳卒中のイベントがないにもかかわらず、多発性に脳梗塞を起こし白質変性を起こして認知症になる場合が多くあります。
認知症はアルツハイマーが最も多いですが、高齢者の場合は脳血管の障害を伴っている場合が多いようです。
生活習慣病の予防が認知症の悪化に大切です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
脳の静脈が詰まる急な頭痛
2018年03月03日
脳の動脈が詰まる病気が脳梗塞です。
脳の静脈が詰まる病気があり、脳静脈洞血栓症といいます。
急な頭痛や嘔吐で発症することがあります。
脳の検査で静脈洞という部位が閉塞しており、場合によっては脳出血を起こすこともあります。
まれな病気ですが、突然の頭痛がある場合は注意する必要があります。
こくぶ脳外科・内科クリニック
てんかん発作と片頭痛
2018年02月24日
てんかんと関連する頭痛として、てんかん発作後頭痛がります。
これは痙攣発作後に起こる頭痛で、比較的よく起こります。
片頭痛がてんかん発作の誘発因子となる場合があり、これを片頭痛てんかんといいます。
片頭痛とてんかんは発症のメカニズムが近い部分もあります。
てんかんのなりやすさは一般の人より片頭痛もちの方が高いと言われています。
こくぶ脳外科・内科クリニック
長引く咳
2018年02月10日
長引く咳で多いのは、ウイルスなどの感染のあとに起こる「感染性咳嗽」です。
それ以外に高齢者の場合は結核やがんなどの可能性もあります。
マイコプラズマなども咳の原因になりますが、流行している場合は注意が必要です。
診断後は抗生物質などによる治療が必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック