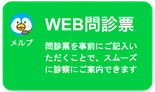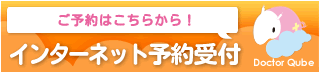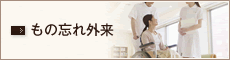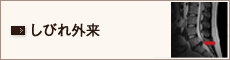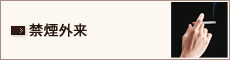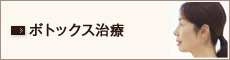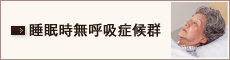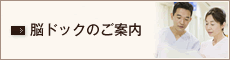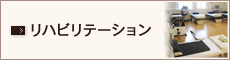認知症に対する運動療法
2016年12月10日
運動と認知症に関してたくさんの論文報告があります。
運動習慣のある人は年をとってから認知症になりにくいようです。
方法としてウォーキングなどの有酸素運動も筋力トレーニングも有効と報告されています。
すでに認知症になっている方は、認知機能の効果は明らかになっていませんがADLはよくなるようです。
運動による脳の血流改善や、神経栄養因子の増加、うつ状態の改善などの関連が示唆されています。
こくぶ脳外科・内科クリニック
尿酸と高血圧
2016年12月03日
尿酸はプリン体から産生されます。
尿酸は痛風の原因となり、単独で動脈硬化の危険因子でもあります。
血圧の高い人が尿酸の値が高いと痛風になるリスクが高いようです。
肥満の解消や、定期的な運動、プリン体の少ない食事、アルコールなどに注意が必要です。
それでも下がらな場合は、投薬にてコントロールが必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
めまいの原因は?
2016年11月26日
めまいの原因として大きく2つに分類されます。
末梢性と中枢性です。
末梢性のめまいは内耳の前庭と呼ばれる部位の障害によるものが多いです。
その中でも良性頭位めまい症が多いです。
中枢性のものは、脳血管障害や脳腫瘍などが原因になることがあります。
中枢性の場合は、めまいに加えて手足のしびれ、運動障害、嚥下障害、しゃべりにくいなどの症状を伴うことが鑑別になります。
こくぶ脳外科・内科クリニック
更年期の高血圧
2016年11月21日
更年期になると血圧が上がることはよく知られています。
原因は女性ホルモンのエストロゲンの低下が関わっていると考えられています。
エストロゲンは血管拡張に働く「NO」という物質に促進的に作用します。
その血管拡張作用が低下するため血管が収縮し血圧が上昇していくようです。
さらにはレニン・アンギオテンシン系の活性化も起こるようです。
血圧上昇時は薬で下げる必要があります。
こくぶ脳外科・内科クリニック
吐き気・嘔吐の原因?
2016年11月12日
吐き気や嘔吐の原因の多くは、胃腸炎など消化器の異常によるものです。
それ以外に、脳からくるもの、めまいによるものなどがあります。
頭痛を伴うものは、脳出血やくも膜下出血なども疑われます。
めまいが回転性の場合に、三半規管の異常のため吐き気を伴うことがあります。
その他、心筋梗塞や糖尿病、薬剤などで吐き気を伴うこともあります。
原因はさまざまですので症状が続く場合は病院で相談を。
こくぶ脳外科・内科クリニック
慢性の咳
2016年11月05日
風邪をひいて咳が続くことがよくあります。
風邪以外にも咳が続く原因があります。
逆流性食道炎の場合は、日中に見られ会話中などに咳がでやすいようです。
夜間や明け方に咳で目が覚める場合は咳喘息が疑われます。
朝起きた時に痰と共に咳が出る場合は肺気腫などが疑われます。
原因によって治療法が変わってきます。
こくぶ脳外科・内科クリニック
低気圧と片頭痛
2016年10月15日
雨の降る前や台風の前に片頭痛がみられることがあります。
頻度として約20%程度の片頭痛もちの人に天気が影響するようです。
気圧の変化に伴い血管が拡張することが頭痛に関係している可能性が指摘されていますが詳細は不明です。
天気に影響される片頭痛でもトリプタンは有効です。
片頭痛の薬は病院でのみ処方できますので、頭痛の症状が強い場合は病院で相談しましょう。
こくぶ脳外科・内科クリニック
足の裏のしびれと痛み
2016年10月08日
足の裏のしびれの中で、親指を含めた内側部は内側足底神経が支配しています。
この領域のしびれと痛みがあれば足底管症候群を疑います。
脛骨神経が足底管と言われる部位で圧迫されることで起こります。
歩いたり運動すると悪化し、安静にすると改善するのが特徴です。
原因として、捻挫や下肢静脈瘤、扁平足、糖尿病などがあります。
こくぶ脳外科・内科クリニック
脳卒中による頭痛
2016年09月24日
頭痛の中で脳卒中は頻度は少ないですが、命に係る頭痛として重要です。
脳卒中の頭痛の特徴として雷鳴性頭痛があります。
突然頭痛が起こり、1分以内にピークのなるのが特徴です。
例えば、脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血、脳内出血、椎骨動脈解離、静脈同血栓症、脳梗塞などがあります。
また今までに経験したことのないような激しい頭痛は脳卒中の可能性があり詳しい検査が必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
足の浮腫み
2016年09月17日
足が浮腫むことはよくありますが、さまざまな原因があります。
気を付けないといけないのは、心臓、腎臓、肝臓など異常からくる浮腫みです。
その他、甲状腺機能低下症、糖尿病のある人もむくみやすいです。
高齢者の場合は、薬の副作用例えば痛み止めや血圧を下げる薬でもなりやすいです。
若い女性で夕方になると足に浮腫みがでる場合は、特発性浮腫が多いです。
症状に合わせて治療が必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック