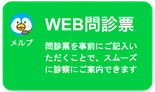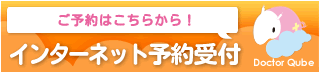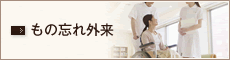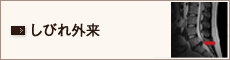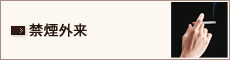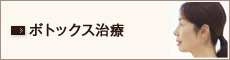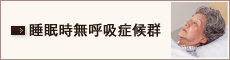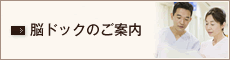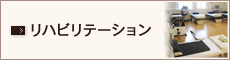慢性頭痛に効く注射薬
2015年03月07日
片頭痛や群発頭痛のある方にトリプタンの注射が有効な場合があります。
片頭痛では内服薬では十分効果がない場合や嘔吐が続いて薬が飲めない場合に使う
場合があります。
注射は自分で自宅でしてもらうことになります。
トリプタンの内服を行っている場合は24時間の間をあけて注射を使う必要があります。
こくぶ脳外科・内科クリニック
片頭痛のアンケートの結果です。ご参照ください。
理学療法士さんを募集しています。
2015年03月02日
常勤の理学療法士さんを募集しています。
脳卒中後遺症、各種痛みの治療が中心になります。
パワープレートを用いたリハビリを行っており、興味のある方はご相談ください。
こくぶ脳外科・内科クリニック
お電話で:087-875-2255
片頭痛アンケート
2015年02月28日
片頭痛のある方にアンケートをお願いしました。
当院通院中の方のアンケートデータも含まれています。
片頭痛は一般的に言われているように30代40代の女性に多いようです。
頭痛が起こる前に首筋が張ってくる、光音に過敏になる、体がだるくなるなどの症状が多いようです。
トリプタン製剤を飲む前の参考の症状になると思います。
頭痛時の市販薬は、やはり頭痛薬の市場でシェアの多い薬が使われているようです。
頭痛の引き金になるものとして食事はあまり関係ない人が多いようです。
https://www.kokubu-clinic.jp/questionnaire/answer001.html
こくぶ脳外科・内科クリニック
片頭痛薬トリプタンはどのタイミングで使う?
2015年02月21日
通常の痛みどめの薬が効かない場合は、トリプタンという薬を使います。
どのタイミングで薬をのむのかですが、頭痛が始まって早期(できれば1時間以内)に
薬を飲むことが勧められます。
片頭痛が始まる前の前兆期や予兆期にトリプタンを飲むことが効果的かどうかは否定
的な意見が多いようですが、前兆期に飲まないと効果がでない人も実際にいます。
個人差が大きいように思われます。
こくぶ脳外科・内科クリニック
軽度認知障害は将来認知症になるか?
2015年02月17日
軽度認知障害はMCIと呼ばれています。
65歳以上のMCIの人は11-17%いると言われています。
その中で本当の認知症になる人は年間10-15%と言われています。
MCIの状態からもとの正常な状態にもどる人もいます。
現在運動や脳のトレーニングなど認知症にならないためのさまざまな研究がすすめられているようです。
MCIから認知症に移行させないことが大切です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
日本人に適切な認知症予防食
2015年02月09日
認知症を予防するためにいろいろな研究が行われています。
40歳代50歳代の高血圧と糖尿病はアルツハイマーのリスクであり、十分な治療が必
要と言われています。
またどのような食事が認知症の予防に重要なのでしょうか?
「久山研究」では、大豆、豆腐、牛乳、チーズ、野菜などが認知機能保持によいようです。
若いうちから予防することが大切です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
チョコレートが片頭痛を引き起こす?
2015年01月28日
食事性因子が片頭痛を起こすことはよく知られています。
赤ワインやチーズなどは有名です。
食物の中のアミンを含むものに片頭痛を引き起こしやすいと言われています。
チーズ、チョコレート、柑橘類、ナッツ類などがあります。
片頭痛のある方すべてにみられるわけではなく、食品と片頭痛の関連は有名な割に数
は比較的少ないようです。
こくぶ脳外科・内科クリニック
ー頭痛アンケート協力のお願いー
慢性頭痛のある方にアンケートをお願いしております。
周りの片頭痛の人がどのような状態なのかを知る機会になればと思っておます。
こちらからお願いします。https://www.kokubu-clinic.jp/questionnaire/
片頭痛のある人に低用量ピルは安全か?
2015年01月24日
片頭痛の中には前兆を伴う場合と前兆のない場合があります。
ガイドラインでは前兆を伴うタイプの片頭痛の方はエストロゲンを含む経口避妊薬は禁
忌となっています。
前兆のないタイプの方でも慎重投与となっています。
頭痛が悪化してしまう可能性があり、喫煙や肥満などが伴うと脳梗塞のリスクも上がる
ことが報告されています。
低用量ピルを使う場合は病院で相談を。
こくぶ脳外科・内科クリニック
ー頭痛アンケート協力のお願いー
慢性頭痛のある方にアンケートをお願いしております。
周りの片頭痛の人がどのような状態なのかを知る機会になればと思っておます。
こちらからお願いします。https://www.kokubu-clinic.jp/questionnaire/
ふわふわ感が続く
2015年01月16日
めまい症状の中に、回転性のものや立ちくらみやふらつき感などがあります。
ふわふわする症状が続くという方も多くみられます。
めまいは脳や内耳の三半規管からくる場合がありますが、多くは回転性のめまいです。
ふわふわする症状にともなって動悸や口周囲のしびれなどが伴う場合は、不安障害などのことが多いです。
過換気症候群の既往のある方などは、ふわふわの原因になっている可能性があります。
また高齢者の場合は白内障や糖尿病、足腰の筋力低下などが原因になることもあります。
こくぶ脳外科・内科クリニック
ー頭痛アンケート協力のお願いー
慢性頭痛のある方にアンケートをお願いしております。
周りの片頭痛の人がどのような状態なのかを知る機会になればと思っておます。
こちらからお願いします。https://www.kokubu-clinic.jp/questionnaire/
日本人のどれくらいの人が片頭痛なのか?
2014年12月29日
日本人で片頭痛のある人は8.4%と言われています。
実際の人数は約840万人ということになります。
特に20-40歳の女性に多いと言われています。
30歳代の女性の約20%は片頭痛もちです。
欧米では片頭痛は東洋人より多いようで、ドイツでは約30%という統計もあるようです。
こくぶ脳外科・内科クリニック
ー頭痛アンケート協力のお願いー
慢性頭痛のある方にアンケートをお願いしております。
周りの片頭痛の人がどのような状態なのかを知る機会になればと思っておます。
こちらからお願いします。https://www.kokubu-clinic.jp/questionnaire/