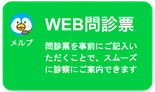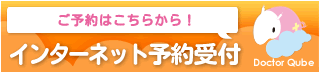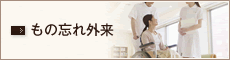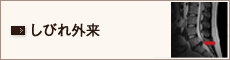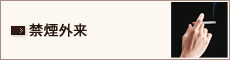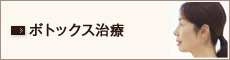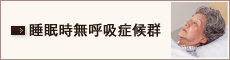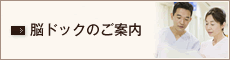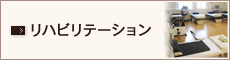タバコにかかる費用
2014年03月22日
タバコの値段は1箱440円程度です。
1日1箱吸って1か月で1万3200円になります。1年で15万8400円になります。
10年で158万 50年吸って792万です。
健康にもよくないので、タバコはやめましょう。
禁煙外来があります。飲み薬を使うとで少しやめやすくなります。
認知症のパーソンセンタードケアとは?
2014年03月15日
パーソンセンタードケアとは、認知症ケアのあるべき姿として、認知症ケアの現場で働く人たちに示した理念です。
以前はスケジュールの沿った時間に縛られた行われていました。着る服も職員が選んで着させていました。
この概念は「その人らしさ」を大切にする考え方だそうですが、その理念はもっと深いものがあるとのことです。
イギリスのキットウッド先生が始めた考え方です。
抑うつ気分の改善に運動が有効
2014年03月08日
うつ病や不安障害などのこころの問題が増えてきていると言われています。
うつ病に関しては定期的な運動が症状の改善によいことは以前から報告されています。
週末にウォーキングなどの運動をするだけでも症状の改善が期待できるようです。
運動の効果は薬物療法、心理療法を比べて同程度の効果があるとも言われます。
運動の習慣がなくて、憂鬱感が続く方は運動をしてみてもよいと思われます。
こくぶ脳外科・内科クリニック
めまいはどこからくるか?
2014年03月01日
めまいを起こす原因は、耳の奥の三半規管や前庭、脳の中の小脳や大脳の異常
の場合があります。
じっとしているとめまいしないけれど、寝返りうをうつなど頭が動いたときにめまいがす
る場合は耳からくる場合が多いです。
若いときに片頭痛がある場合は、ある程度年齢がいってからめまい症状がでる場合
もあります。この場合は片頭痛の治療が必要になります。
高齢の方のめまいは三半規管や前庭の老化によりめまい症状がみられることもあり
ます。
症状が続く場合は一度病院で診断してもらいましょう。
こくぶ脳外科・内科クリニック
足のしびれ
2014年02月22日
しびれは脳から、脊髄から、末梢神経からその他循環障害などで起こります。
脳梗塞など脳からくるしびれは半身の症状に一部として足がしびれることが多いで
す。
足の外側がしびれる場合は腰椎椎間板ヘルニアなど腰が原因で起こります。
その他糖尿病などにより足の神経を栄養する血管が障害され、しびれがみられること
があります。
しびれにもさまざまな原因がありますので、診断を行ってからの治療が必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
認知症とうつ病
2014年02月01日
認知証の中にはアルツハイマー病 レビー小体型認知症、脳血管性認知症などがあ
ります。
認知症に伴う精神症状などをBPSDと言いますが、その中にうつ病もあります。
アルツハイマー病の約半数にうつ病を伴うという報告もあります。
またうつ病をもっていると、認知症に将来なるリスクも高くなると言われています。
うつ病のストレスが海馬を委縮させたり、アミロイドβタンパクの蓄積を進めるのではな
いかと考えらています。
こくぶ脳外科・内科クリニック
糖尿病の治療は認知症予防になる?
2014年01月25日
糖尿病はアルツハイマー病、血管性認知症の危険因子です。
ガイドラインでは中年期(認知症になる前)の糖尿病が高齢期のアルツハイマー病の
危険因子となっています。
高齢になってからの糖尿病は関係ないと言われています。
肥満やインスリン抵抗性と認知症の関係が注目されていますが、研究段階とのことです。
若いときから糖尿病を管理することが大切です。
肩こりに関係する筋肉
2014年01月18日
肩や首の周囲にはたくさんの筋肉がついています。
首だけで26対の筋肉があります。
さまざまな筋肉は肩首こりに関与していますが、肩甲骨と頸椎にわたる肩甲挙筋、首
肩背中全体にわたる僧帽筋などによります。
猫背で顎をつきだした姿勢を長くとっていると、首回りの筋肉が硬くなり症状がでま
す。
姿勢に注意して定期的なストレッチが大切です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
慢性の肩こり
2014年01月11日
慢性の肩こりは緊張型頭痛の原因のひとつになります。
肩こりの原因にはさまざまのものがありますが、肩甲骨の動きが悪い場合も原因の
一つです。
上肢を挙げたときに肩甲骨は最大60度開きますが、20-30度しか開かない人がい
ます。
肩甲骨周囲の筋肉が硬くなることで動きが悪くなり、肩こりの原因になります。
肩こりの強い人はまずは検査を行って、定期の運動などリハビリが必要です。
こくぶ脳外科・内科クリニック
片頭痛とむくみ
2013年12月28日
片頭痛もちの人はよくわかると思いますが、頭痛が起こる前にいろいろと予兆があり
ます。
食欲が亢進したり、手足の皮膚の違和感がでたり、首が張ったりします。
その中でむくみが出る人もいます。
早い人は頭痛の始まる前日からみられることもあるようです。
片頭痛は頭痛だけの症状でなく、全身にさまざまな変化をもらたすのが特徴です。
こくぶ脳外科・内科クリニック