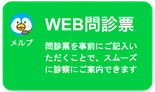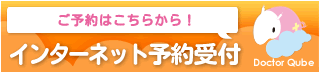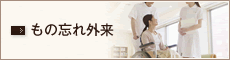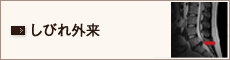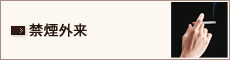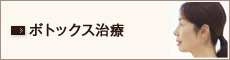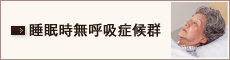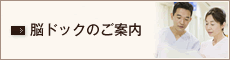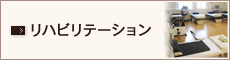脳脊髄液減少症
2011年08月12日
脳脊髄液減少症は、頭痛、頚部痛、めまい、耳鳴り、視力障害、体がだるいなどさまざまな症状を示します。
原因としては交通事故後に起こるものが有名ですが、スポーツ後によるもの、咳や転倒によるもの、排便などいきんだあとなどにも起こります。脳脊髄液が外に漏れることによってさまざまな症状が起こります。
診断にはMRI検査が有効ですので、疑いのある方は病院で検査しましょう。治療としては、ブラッドパッチが有名ですが、カフェインやテオフィリンなどの飲み薬が有効なことがあるようですのでまずは試してみてもよいのではないでしょうか。
お問い合わせはこちらから https://www.kokubu-clinic.jp/contact/
こくぶ脳外科内科はイオンタウン国分寺にあります。
2011年08月11日
高松市国分寺町のイオンタウン国分寺ショッピングセンター内にクリニックがあります。
頭痛、物忘れ、しびれ、めまいなど脳の病気が心配な場合はご相談ください。その他、高血圧、糖尿病、高コレステロールなどの生活習慣病、風邪や腹痛、下痢、発熱など一般内科の場合もご相談ください。
500台置ける駐車場があります。
お問い合わせはこちらから https://www.kokubu-clinic.jp/contact/
睡眠障害でアルツハイマーのリスク上昇
2011年08月10日
アルツハイマー病の原因は脳へのベータアミロイドの蓄積が関与しているといわれています。(アミロイドが増えても認知症にならない人もいます。)夜しっかり寝ると朝にはベータアミロイドは分解されています。しかし夜寝れないと脳の中にアミロイドが溜まっていき、アルツハイマー病になりやすくなるといわれています。
日本人は世界の中でも睡眠時間が短いといわれています。時間は人によって違いますが、十分な睡眠時間を確保しましょう。睡眠を十分にとることがアルツハイマー病の予防になります。
睡眠不足は内臓脂肪の蓄積にも関わっています。
帯状疱疹後の痛みに漢方薬
2011年08月09日
帯状疱疹後の痛みは治りにくいですが、通常の痛み止めが効かない場合は漢方薬の抑肝散が効く場合があるようです。この漢方薬は認知症の周辺症状に使うこともあります。脊髄の下降抑制系の活性化によって、痛みをコントロールするのではないかと考えられていますが、詳細は不明です。痛みが改善しない場合は試してみてもよいかもしれません。
片頭痛に対するボトックス注射
2011年08月09日
難治性の片頭痛に対してボトックス注射が有効であることが報告されています。最近アメリカではその有効性のため保険適応にもなったようです。その効果は頭部の感覚神経の末端に薬が作用して、痛みを改善させるのではないかと考えられています。効果には個人差もありますが、飲み薬の副作用等で薬が使えない方は試してみてもよい方法かもしれません。ただし日本では保険が効きませんので自費診療になります。
頭部打撲の脳への影響
2011年08月08日
アメリカンフットボールの選手は脳震盪を起こすことが多いですが、将来アルツハイマー病になるリスクが数倍高いと報告されています。脳震盪を起こすほどの強い頭部打撲を繰り返していると、神経細胞へのダメージがありアルツハイマーを起こすと考えられます。若いときの頭部打撲があとになって症状を起こしてくるので、脳を普段から保護するように注意することが大切です。
運動による脳への影響
2011年08月06日
歩いたり、走ったり、泳いだりと体を動かすことが体によいことはなんとなくわかります。運動することが脳にも良いことが注目されています。定期的な運動をすることで、脳の海馬というところで、脳由来神経栄養因子(BDNF)が増えると報告されています。BDNFは神経への栄養剤のような働きをします。老齢期になってもBDNFは増えるようです。アルツハイマー病では海馬が特に障害されますが、運動することにより予防効果が期待されます。1日30分×5日/週程度の運動が効果的のようです。
アルツハイマーの予防法は常に頭を使うこと
2011年08月05日
歳をとっても脳を使うことで認知症を予防することができるという報告がたくさんあります。特にいままでしたことがないことを始めることが脳の刺激になるようです。昔から脳は外敵に常に目を光らせている必要性から、新しいもの、珍しいものに敏感に反応する脳の機構をもっています。その時神経細胞は突起を伸ばしていきます。このことが認知症の予防効果になるようです。歳をとっても何か新しいことに挑戦しましょう。
授乳中の頭痛薬の飲み方
2011年08月04日
ほとんどの薬剤は母乳中に移行することが知られています。しかし実際には少量しか移行しないと言われています。ロキソニン、カロナール、トリプタンなどは頻回でなければあまり問題ないと報告されています。
ただし全く安全というわけではありません。授乳後または搾乳後に薬を飲むこといよって、次の授乳までの間があくことにより、より安全性が増すと思われます。
緊張型頭痛のメカニズム
2011年08月03日
緊張型頭痛の発症メカニズムはまだわかっていないことが多いですが、末梢性のメカニズムと中枢性のメカニズムが関与していると言われています。末梢性とは頭と首の筋肉の緊張に伴うものですので、筋緊張をとることが治療になります。また慢性化した頭痛の場合は、中枢性のメカニズムが関与しており、脳からの筋収縮を抑制する経路の働きが悪いと考えられています。
治療としては肩こり頭痛体操、、飲み薬による治療が必要です。