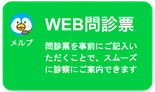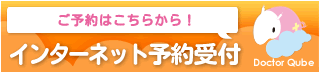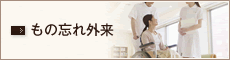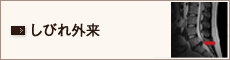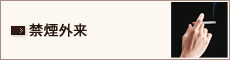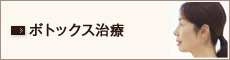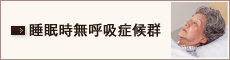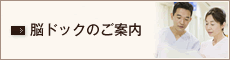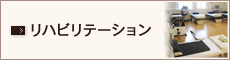片方の耳鳴りと難聴がある場合
2011年06月15日
年齢と共に耳鳴りが出てきた方が多いと思います。耳鼻科で検査をして頂いて異常ないといわれた場合は多くは老化に伴うもので、治らないことが多いです。
片方の耳鳴りと難聴(聞こえにくい)がある場合は、脳の中に原因がある場合があります。聴神経腫瘍といって、耳の神経に腫瘍ができることがあります。小さいものだと脳のMRI検査だけではわからないことがあり、造影の検査が必要な場合もあります。
症状が気になる方は一度病院で相談してみましょう。
最近視野が狭くなった気がする
2011年06月14日
最近物が見えにくい症状があり、眼科では異常ない場合は脳が原因の場合があります。物を見る場合は、目からの情報は視神経を通って脳の後頭葉というところに行きます。その情報が伝わるまでに異常があれば、視野が狭くなる場合があります。視野が狭いとは、最近よく人にぶつかるなどの症状として出ます。原因の一つは下垂体腺腫という脳腫瘍です。これが視神経を圧迫することでものが見えにくくなることがあります。また後頭葉にできた脳腫瘍や脳梗塞などが原因で同じような症状をきたすことがあります。
症状が改善しない場合は脳の検査もしてもらいましょう。
慢性の頭痛と何事も楽しめない?
2011年06月13日
最近頭痛やめまい感などが続くとのことで病院に来られる方がいらっしゃいました。話をよく聞くと、不眠があって夜よく目が覚めるとか、趣味など何事も楽しめないなどの症状がありました。また日中もいらいら感や不安感があるとのことで軽症のうつ病の可能性が考えられます。
うつ病をベースとした慢性の頭痛は比較的多いと言われています。鎮痛薬を飲んで一時的にはよくなりますが、長期的には改善しません。抗うつ薬などの治療が効果的な場合があります。症状が続き困られている場合は早めに病院で相談しましょう。
高血圧とかくれ脳梗塞
2011年06月11日
かくれ脳梗塞とは麻痺や言語障害がなくても脳のMRI検査をすると脳梗塞ができているものを言います。慢性の高血圧がある方にかくれ脳梗塞ができやすいと言われています。血圧の薬を飲んでいても血圧が高めの人は注意が必要です。血圧が高めの方は定期的に脳のチェックをしておきましょう。脳梗塞を起こしている方は早めに血液さらさらの薬を飲むことで再発を予防することができます。
MRIとCTの違い
2011年06月10日
MRIは磁石を使って体の中を撮影します。CTは放射線(エックス線)を使って撮影を行ます。それぞれ得意不得意があります。例えば脳の検査で言えば、MRIでは細かい撮影ができて、脳の血管撮影が造影剤なしで可能です。一方で出血の有無や骨を見ることは得意ではありません。CTではスクリーニング的に全身の撮影をすることが可能ですが、被爆をしますので、頻回に撮影すると問題が発生します。一般には状況にあわせて使いわけが行われています。
新しい認知症の薬
2011年06月09日
新しい認知症の薬メマリーが発売になりました。今までは脳の中のアセチルコリンを増やす薬しかありませんでしたが、新しいメカニズムの薬です。過剰なグルタミン酸の作用を抑えることによって神経細胞死を抑える効果があるようです。そのため認知症の進行予防に効果的です。また怒りっぽいなどの症状も抑えてくれる効果があるようです。認知症が中等度以上ある方は、いままでの薬と併用してはどうかと思います。
肩こりに効くサプリメント
2011年06月08日
肩こりは首から肩にかけての血流が悪くなり、疲労物質がたまることによっておこると考えられています。
サプリメントの中でビタミンEは全身の血流を良くする効果があり、首から肩にかけての血流も良くして肩こりを改善させる可能性が考えられます。またビタミンB1は肩にたまった疲労物質を分解する効果もあるようですので肩こりに有効と思われます。
いずれにしても普段から姿勢をよくする、適度な運動をすることが大切です。
うつ病と頭痛
2011年06月07日
うつ病と頭痛には相関関係があるといわれています。この場合の頭痛は、鎮痛薬でコントロールするのではなくて、うつ病の治療が必要です。うつ病の診断として2質問法という方法があります。1)この1ヶ月気分が沈んだり、憂鬱な気分になったことがあるか?2)この1ヶ月間物事に対して興味がなくなったり、心から楽しめなくなったか?。
この2つのどちらかがあればうつ病の可能性も考えられます。頭痛を伴っている場合は、うつ病に関連した頭痛の可能性もあると考えられます。
慢性頭痛・肩こりの原因としてのジストニア
2011年06月06日
慢性頭痛の原因として肩こりがありますが、その肩こりの原因としてジストニアが関わっている場合があるようです。痙性斜頚はジストニアの一種で首の位置が勝手に動いてしまう病気ですが、首が動かないまでも首の筋肉が過剰に収縮して痛みを引き起こすことがあります。原因としては大脳基底核といわれる部分の異常が考えられています。薬をのんでも改善しない持続する肩こり頭痛がある場合はジストニアも考えて治療をする必要があるようです。治療としては、鎮痛薬ではなくジストニアの薬またはボトックス治療が効果があります。
増加するアテローム血栓性脳梗塞
2011年06月04日
脳梗塞は臨床的に3種類に分かれます。ラクナ型、アテローム型、心原性の3種類です。昔はラクナ型が多かったのですが、最近は動脈硬化によって起こるアテローム型が増えています。高血圧や糖尿病など生活習慣病が原因で脳の血管の動脈硬化がすすみ、脳梗塞を起こしてきます。
予防としてやはり血圧の管理や糖尿病の管理が大切になってきます。血管がかなり細くなっている場合は血液さらさらの薬を飲む必要があります。診断には脳のMRI、MRA検査が必要です。
以前から血圧が高い方や糖尿病のある方は脳の検査が必要な場合がありますのでご相談ください。